子どもの頃に遊んだ「かごめかごめ」が、実は徳川埋蔵金の隠し場所を示す暗号だったとしたら…?
そんな話を聞いて、「本当かな?」と思いながらもワクワクしていませんか?
この記事では、あの謎めいた歌詞が持つ驚くべき意味と、徳川埋蔵金との関連性を徹底解説します。
「籠目」が六芒星(ヘキサグラム)を表すことや、徳川ゆかりの地を結ぶと地図上に六芒星が浮かび上がることなど、偶然とは思えない数々の符合から、日光東照宮に秘められた財宝の可能性まで探ります。
都市伝説好きなあなたも知らなかった「かごめかごめ」の真実が、ここにあります。
かごめかごめを広めたのは松尾芭蕉という説も。
20兆円相当とも言われる徳川埋蔵金の謎に、一緒に迫ってみませんか?
かごめかごめとは?その歌詞と変遷

「かごめかごめ」は日本の伝統的な童謡であり、子どもたちに親しまれてきた遊び歌です。
一人が目隠しをして中央に座り、他の子どもたちが手をつないで輪になって回りながら歌い、最後に後ろにいる人を当てるという遊び方で知られています。
子供の頃にやったことがあるという方も多いのではないでしょうか。
現代で一般的に知られている歌詞は以下の通りです。
しかし、この歌詞は時代と地域によって様々なバリエーションが存在していました。

正直、私は「後ろの正面だ~あれ」の部分しか意識してなかったです。
江戸中期(1751年~1772年頃)に記録された最古の歌詞とされるものは、「かァごめかごめ かーごのなかの鳥は いついつでやる 夜あけのばんに つるつるつっぺぇつた なべのなべのそこぬけ そこぬいてーたーァもれ」と現代のものとはかなり異なります。

鍋の底抜けってもはや今の遊び方と異なっていたのでは?と思ってしまいますね。
また地域によっては「ヒト山 フタ山 ミ山越えて ヤイトをすえてやれ熱つや」といった部分が追加されたり、「鶴と亀が滑った」が「鶴と亀が統べった」になるなど、微妙な違いがありました。
この童謡の起源については諸説あり、江戸時代中期には既に存在していたとされていますが、全国的に広まったのは比較的新しく、昭和初期に千葉県野田市の歌が標準となったという説もあります。
歌詞の意味が謎めいていることから、後に様々な都市伝説が生まれる素地となりました。
かごめかごめを広めたのは松尾芭蕉?

「かごめかごめ」を全国に広めたのは松尾芭蕉だったという説があります。
この説によれば、松尾芭蕉の正体は実は徳川家康に仕えた忍者・服部半蔵だったというのです。
服部半蔵は家康に「自由に日本を旅したい」と願い出て許可を得た際、条件として「かごめかごめ」の歌を全国に広めるよう命じられたとされています。
忍者が俳聖に変装して秘密の暗号を広めるなんて、映画のようなストーリーですよね。
しかし、歴史的事実を確認すると、この説には大きな矛盾があります。
服部半蔵は1596年に没していますが、松尾芭蕉は1644年生まれ。
両者の生存期間には重なりがありません。
ちょっと信じてしまいましたが、歴史の真実は時に残酷なものです。
また、芭蕉の旅のスピードについても「1日200km移動」という非現実的な説がありますが、実際は1日十数キロ程度で十分説明がつきます。
これは忍者ではなく、一般人でも十分可能な距離ですね。
それでも「かごめかごめ」が短期間で全国に広まった経緯は不明な点が多く、何らかの組織的な意図があったのかもしれません。
徳川埋蔵金の謎

徳川幕府の財宝はどこへ消えたのか?
江戸時代の終焉とともに姿を消したとされる莫大な財宝「徳川埋蔵金」は、数百年にわたって人々の想像力をかき立ててきました。
この謎めいた財宝の正体と、その所在をめぐる有力な仮説について探ってみましょう。
徳川埋蔵金とは何か?
徳川埋蔵金とは、江戸幕府が明治維新の際に隠したとされる巨額の財宝です。
正直、これほど日本人をワクワクさせる都市伝説は他にないのではないでしょうか!
1868年4月、江戸城が無血開城となった時、財政難に苦しむ明治新政府は徳川家の財政基盤を期待していました。
なんと、城内の金蔵は空っぽだったのです!
彼らの心境を想像すると、宝くじの高額当選を確信して喜び勇んでいたところ、「はずれ」だった瞬間のようなショックだったに違いありません。
当時の幕府には軍用金として360万〜400万両(現在の価値で約20兆円相当)があったとされています。
今の価値で20兆円ですよ!
私なら絶対に隠しますね(笑)。
この記録は幕府の重臣である勝海舟の日記にも記されており、「常備兵を養うための金で使うわけにはいかない」という記述が残っています。
なぜこの財宝が隠されたのか?
その背景には、徳川家が将来的に幕府を再興するための資金として温存しておきたいという思惑があったとされています。
また、一説によれば、新政府に渡さないよう隠匿するよう指示したのは、幕府の大老を務めた井伊直弼だったという説も。
いずれにせよ、明治維新から150年以上が経過した現在も、この埋蔵金は見つかっていないと言われています。
もし見つかっていても公表されていないだけと言うこともあるかもしれません。
存在そのものを疑問視する声もありますが、勝海舟の記録から、その実在性については相応の根拠があると考えられています。
私個人としては、単なる伝説で終わらせるには惜しいほど魅力的なストーリーだと思います。
赤城山説

徳川埋蔵金の隠し場所として最も有名なのが、群馬県の赤城山です。
この説が広まったのは、井伊直弼が幕府の将来を憂い、非常時に使用するための資金として赤城山への埋蔵を計画したという伝承があるためです。
井伊直弼といえば、桜田門外の変で有名ですが、実は埋蔵金の立役者だったかもしれないなんて、歴史の教科書では教えてくれませんよね。
実際に、テレビ番組などでも赤城山での発掘調査が行われ、徳川家康の黄金人形のようなものが発見されたこともあります。
しかし、これは本来の埋蔵金ではなく、むしろ「ダミー」だったのではないかという見方が強まっています。
古来より埋蔵金は、本命とダミーの2〜3カ所に分けて隠すという知恵があったようです。
赤城山で見つかったものはそのダミーであり、本当の埋蔵金はまだ見つかっていないという説が浮上しています。
江戸時代の人々の知恵は侮れませんね。
だけど本当にダミーを隠したとすると、本物がある可能性も高いのかもしれません。
かごめかごめと徳川埋蔵金を結ぶ暗号

子どもの遊び歌として親しまれてきた「かごめかごめ」ですが、実はその歌詞には徳川家の埋蔵金の在り処を示す暗号が隠されているという都市伝説があります。
一見無邪気な童謡が、莫大な財宝への地図だったとしたら?
その謎めいた関係性を紐解いていきましょう。
「籠目(かごめ)」と六芒星の秘密
「かごめ」という言葉を聞くと、多くの人は子どもの遊び歌を思い浮かべるかもしれませんが、その背後には想像を超える深遠な世界が広がっているんです。
「かごめ」の本来の意味は、竹や藤などで編んだ籠(かご)の目のこと。
この一見シンプルな編み目模様が形作る特徴的な形は、実は六芒星(ヘキサグラム)という神秘的な幾何学模様なんです!
日本の伝統模様「籠目紋」として知られるこの形は、二つの三角形が重なり合った姿をしていますが、この形状が実は意味を持っています。
この六芒星、実は世界中で神秘的パワーを持つシンボルとして崇められてきたんですよ。
ユダヤ教では「ダビデの星」、西洋魔術では「ソロモンの印」と呼ばれ、古代から守護や封印の象徴として使われてきました。
日本の神社仏閣でもこの形を見かけることがありますが、それは決して偶然ではないんです。
魔除けや結界として日本人も古くからこの形状の力を信じていたんですね。
特に興味深いのは、徳川埋蔵金の隠し場所を示す暗号として「かごめかごめ」が使われたという説です。
この「籠目=六芒星」という図形が地図上に描かれると、その中心や特定の頂点に財宝があるという解釈。

六芒星の中心には「守るべき最も重要なもの」が置かれるという象徴性も、この説をより説得力あるものにしています。
個人的に最も興味をそそられるのは、六芒星が「封印」や「秘密を守る」ためのシンボルとして使われてきた歴史です。
徳川家が膨大な家宝を守るために籠目紋を使った暗号を考案したという説は、歴史ロマンとしても胸躍るものがありますよね。
もしかしたら、私たちが子供の頃から歌ってきた「かごめかごめ」には、想像を超える秘密が隠されているのかもしれません。
徳川ゆかりの地を結ぶ地図の謎
徳川家ゆかりの重要な神社仏閣を地図上で線で結ぶと、なんと六芒星(籠目)の形になるという噂が。
そしてその六芒星の中心にあるのが日光東照宮だと言われています。
これが単なる偶然だとは、どうしても思えません。
これらの場所が六芒星を形作るように配置されているのは、徳川家が何かしらの意図を持って計画したのかもしれません。
日光東照宮と「かごめかごめ」の歌詞の符合
「かごめかごめ」の歌詞と日光東照宮の関係を調べれば調べるほど、その一致点の多さに驚かされます。
「籠の中の鳥は」という歌詞は、「籠目の中の鳥居」と解釈できるというのは本当に目からウロコでした。
六芒星の中心にある日光東照宮の鳥居を指すという説は、単なる言葉遊びを超えた説得力があります。
さらに衝撃的なのは「夜明けの晩に鶴と亀が滑った」という部分です。
東照宮には実際に鶴と亀の像があるんですよ!
しかも、朝日が昇る時間帯にこれらの像に光が当たると、影が特定の方向に伸びるのです。
童謡の「かごめかごめ」って何かの暗号って言われてるんですけど
栃木県の日光東照宮に鶴と亀がいて、夜明けの晩=明け方?朝日🌅が徳川家康公のお墓を照らす(らしい)事から徳川埋蔵金のありかを示してるという説(埋蔵金がもしあるならわざわざヒント伝えなくね?)もあったり…
神話的な話だと… pic.twitter.com/gdhWXK65fZ— シロ@秋田犬達と森暮らし (@moonstaremblem) January 19, 2025
その方向には徳川家康の墓があるというから驚きです。
これが偶然だとしたら、あまりにも出来すぎていると思いませんか?
「後ろの正面だあれ」という謎めいた歌詞も、鶴と亀の像の後ろにある家康の墓を指す暗号だと考えると、すべてのピースがぴったりとはまります。
さらに興味深いことに、墓の近くには上部が欠けた六芒星の紋様があるという情報もあります。
上が欠けているということは「下を見よ」という指示とも解釈でき、墓の下に埋蔵金があるのではないかという憶測も生まれています。
地質調査によれば、東照宮の敷地内には地下に何かが埋まっている形跡があるとのこと。
これは本当に興味をそそられる情報ですね。
ただ、文化財保護の観点から大規模な発掘調査は行われていないため、その正体は依然として謎のままです。
個人的には、この謎が永遠に解明されないままの方が、ロマンがあって良いようにも思えますが…。
「かごめかごめ」の歌詞と日光東照宮の間にこれほど多くの符合点があることは、偶然とは思えません。
六芒星の示す場所について考察
六芒星の頂点を示す場所が具体的にどこなのかが明らかになっていません。
そこで徳川家にゆかりのある地で六芒星を描いてみました。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| ①日光東照宮 | 徳川家康(東照大権現)を主祭神として祀る、東照宮の総本社 |
| ②江戸城 | 江戸幕府の政庁および徳川将軍家の居城 |
| ③久能山東照宮 | 徳川家康を神様として祀る東照宮の発祥の神社 |
| ④大樹寺 | 家康公の先祖である松平家・そして徳川将軍家の菩提寺 |
| ⑤尾崎神社 | 徳川幕府から徳川家康を祀ることを許され、1643年に建立した神社 |
| ⑥佐渡金山 | 1603年に徳川家康が佐渡島を幕府の直轄地とし、鉱山の開発を本格的に開始 |

やや歪ではありますが、六芒星が浮かび上がりました。
この中の①日光東照宮に徳川埋蔵金があるという説が有力となっていますが、果たしてどうなのでしょうか。
かごめかごめの歌詞からすると、日光東照宮までたどり着けば理にかなっているとも思えます。
しかし、肝心の日光東照宮までのプロセスが曖昧となります。
徳川家にゆかりのある地というのは、かなり多く存在しているのです。
結果的に六芒星を描くことは可能ですが、表の説明を見てわかるように、その場所の由来がバラバラです。
例えば全国の東照宮の位置が六芒星を描けば信憑性が高まるかもしれません。
ですが、残念ながら全国の東照宮の位置からは六芒星は発見できず、上の図で描いた六芒星は単にストーリーを完成させるために抽出したに過ぎないのです。
よって徳川埋蔵金が日光東照宮にあるという説はあくまで都市伝説に過ぎないと感じます。
徳川埋蔵金は本当に存在するのか

ここまで徳川埋蔵金のなぞについて解説してきましたが、気になるのは本当に今も埋蔵金が眠っているのかということになりますね。
個人的な見解は、埋蔵金は眠っていない!
理由としては、隠したからには必ず回収しようとするからです。
勝海舟の記録に残っていたということは、ほかにも記録されていた可能性や、埋蔵金の存在を知っていた人がいたと考えることが出来ます。
だとすると何事も無かったかのように、跡形もなく消えている可能性もあるのではないでしょうか。
ただし、明治新政府の目が光っていたせいで、掘り起こすことが叶わなかったと考えることもできます。
そっちの方がロマンがあって良いですよね。
かごめかごめにまつわる都市伝説

「かごめかごめ」は埋蔵金の暗号以外にも、様々な不気味な都市伝説を持つ童謡として知られています。その謎めいた歌詞と独特な遊び方から、時代を超えて多くの解釈が生まれてきました。
最も有名な説の一つが「流産説」です。
「かごめ」が妊婦を、「籠の中の鳥」が胎児を意味するという解釈は、この歌の印象を一変させます。
特に「鶴と亀が滑った」というフレーズが、姑が嫁を階段から突き落として流産させる様子を表しているという説明は、江戸時代の厳しい家父長制度の闇を想起させます。
そして最後の「後ろの正面だあれ」が「誰が背中を押したのか」という問いかけだと解釈すると、この歌全体が恐ろしい家庭内の悲劇を描いているように思えてきます。
また「罪人説」では、この歌が処刑を待つ囚人の様子を描いているとされます。
江戸時代の厳しい刑罰制度を考えると、この解釈にも一定の説得力があるんですよね。
「籠の中の鳥」を牢屋に閉じ込められた罪人と見なし、「いついつでやる」を「いつ処刑されるのか」という死の恐怖を表現していると考えると、子供たちが無邪気に歌う光景とのギャップに背筋が寒くなります。
特に「後ろの正面だあれ」が処刑後の首を模倣するという説には、本当に戦慄を覚えます。
実際に江戸時代の子供たちが処刑の様子を見て、それを遊びに取り入れていたという歴史的背景を考えると、この説もあながち荒唐無稽とは言えないのです。
中でも私が最も恐ろしいと感じるのは「口寄せの儀式説」です。
一人が中央に座り、周りを囲んで回るという遊び方には、降霊術の要素が含まれているというのです。
中央の子が依代となり、霊を呼び寄せる儀式を子どもたちが知らずに行っていたという説は、「こっくりさん」などの占いと同様の恐ろしさを感じさせます。
これらの都市伝説は時代背景や歴史的事実との整合性に欠ける部分もあるのは事実です。
しかし、そうした矛盾点があるにもかかわらず、これらの説が人々の間で広まり続けるのは、「かごめかごめ」の歌詞が持つ本質的な不気味さと謎めいた雰囲気があるからでしょう。
「後ろの正面」という言葉の矛盾や、「いついつでやる 夜明けの晩に」という時間の混乱は、現実世界のルールが適用されない、何か別の次元を暗示しているようにも感じられます。
まとめ

「かごめかごめ」は単なる子どもの遊び歌ではなく、徳川埋蔵金の在処を示す暗号ではないかという都市伝説は、歴史ロマンとして多くの人を魅了しています。
「籠目」という言葉が六芒星(ヘキサグラム)という神秘的なシンボルを表し、この形状が世界中で守護や封印の象徴として使われてきた事実は、この説の土台となっています。
特に驚くべきは、徳川ゆかりの地を地図上で結ぶと六芒星が形成され、その中心に日光東照宮が位置すること。
しかしながら、六芒星を示す具体的な要素は判明しておらず、デマである可能性も否定できません。
一方、「かごめかごめ」には流産説、罪人説、口寄せの儀式説など不気味な都市伝説も存在します。
これらの説は歴史的整合性に欠ける部分もありますが、歌詞の本質的な不気味さが人々の想像力を掻き立て続けているのです。
埋蔵金は本当に眠っているのか?
私は見つからないままの方がロマンがあっていいと思います。

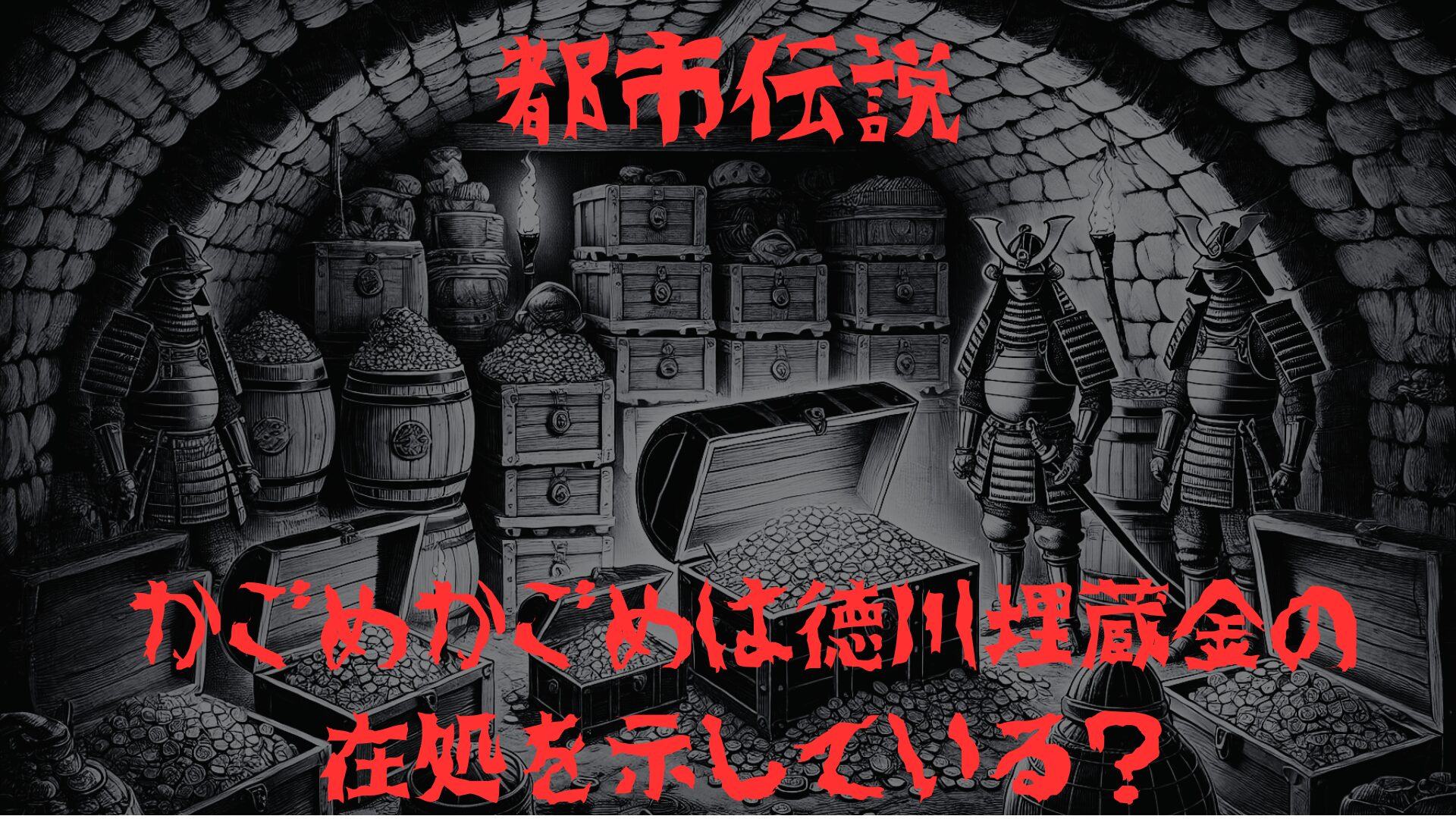



コメント