「子供の頃に見たアンパンマンの絵本が怖かった」「なぜこんなに怖い設定だったの?」そんな記憶を持つ方も多いのではないでしょうか。
2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の放送を前に、初期アンパンマンの知られざる設定と、その深い意味について解説します。
アンパンマンの初代作品と言われている『十二の真珠』では、主人公であるはずのアンパンマンが死ぬという驚きの設定がありました。
それから3年後の1973年に登場した絵本「あんぱんまん」にも驚くべき設定が数多く存在していました。
8頭身の不気味な姿で空を飛び、顔を直接かじらせる描写。
時には顔が完全になくなっても活動を続けるなど、現代の親子が目にすれば驚くような表現が随所に見られます。
しかし、これらの「怖い」表現には、実は深い意味が込められていました。
それは作者やなせたかし氏が追求した「自己犠牲の精神」と「逆転しない正義」という理念です。
時代とともに表現方法は変化しましたが、その本質は今も脈々と受け継がれています。
本記事では、アンパンマンの進化の歴史を、当時の貴重な資料や関係者の証言をもとに詳しく解説。
なぜそのような表現が必要だったのか、そしてどのように今の姿へと変化していったのか、その真相に迫ります。
アンパンマン初期の設定が怖い?
2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の放送を控え、アンパンマンへの注目が集まっています。
しかし、私たちが知っている明るく優しいアンパンマンは、実は誕生から大きな進化を遂げているのです。
1973年から絵本で描かれた初期のアンパンマンには、現代の親子が目にすれば驚くような衝撃的な設定が数多く存在していました。
中国製じゃなくて初期アンパンマンはこうだったのね。まつ毛も指もある。 pic.twitter.com/T8D9r3eens
— ユー(温泉) (@2oy5KpSD0ggwoz9) February 2, 2025
中でも特に印象的なのが、アンパンマンの「顔」にまつわる描写です。
現在のアニメでは、アンパンマンは困っている人に顔の一部をちぎって優しく手渡します。
しかし、初期作品では空腹の人に直接顔をかじらせるという、かなり生々しい表現が使われていました。

なかなか食べてもいいよと言われても直接顔を食べるのは抵抗ありますよね。
さらに驚くべきことに、顔を食べられた後も普通に会話し、飛行することができたのです。
初期アンパンマン、ちょっと怖いけど顔全部食べられても普通に生きてるの凄い笑
水で顔が濡れると力が出ないのにねぇでも、物語が素朴でお腹を空かして困ってる人がいないか見回ってる設定も好き👍#初期アンパンマン#絵本#癒された pic.twitter.com/iYesZSPEWa
— 🍅三浦あり(しおぴー)@絵本作家みさわしおり)🍅 (@miuraari) February 23, 2025
さらに今と違って8頭身の細長い体型に、人間そっくりの5本指。
現代の3頭身でグローブのような手のデザインとは似ても似つかない姿でした。
個人的には、このアンパンマンを見たとき、某有名なホラー映画のキャラクターを思い出してしまい、背筋が寒くなりました。
当時の世間の反応も興味深いものです。
幼稚園の先生からは「残酷すぎる」と批判の声が。
絵本評論家は「図書館に置くべきではない」と一蹴。
編集者までもが「これっきりにして」と難色を示したそうです。
ところが、驚くべきことに子どもたちの反応は大人たちの予想を完全に裏切りました。
幼稚園では取り合いになるほどの人気を博し、図書館でも常に貸出中の状態が続いたのです。
なぜ子どもたちはこれほど夢中になったのでしょうか?
実は、この「怖い」と評される表現の数々には、深い意味が込められていました。
それは「自己犠牲の精神」と「逆転しない正義」という、作者やなせたかし氏の強い思いです。
空腹で苦しむ人を前にして、見て見ぬふりをしない。
たとえ自分が傷つこうとも、困っている人を助ける。
その純粋な愛の形を、あえて衝撃的な表現で描き出したのです。
私たち大人は時として「怖い」「残酷」という言葉で物事を簡単に否定してしまいがちです。
しかし、子どもたちは本能的に、その表現の奥にある真実の愛を感じ取っていたのかもしれません。
初期はアンパンマンの顔が無くなっていた

リアルタイムではないですが、1973年の絵本『あんぱんまん』を子供のころに初めて見た時の衝撃は、今でも鮮明に覚えています。
現代のアニメで見慣れた優しい表情のアンパンマンとは全く異なる、なんとも言えない不思議な雰囲気が漂っていたのです。
最も印象的だったのは、砂漠での一場面です。
アンパンマンが旅人に向かって「さあ、ぼくのかおをたべなさい」と差し出すシーン。
旅人は最初「そんなおそろしいことはできません」と躊躇しますが、アンパンマンに促され、ついに顔の半分を食べてしまいます。
さらに衝撃的なのは、その後、顔がすでに半分くらいになったアンパンマンが、森の中で迷子になった子供を救うというシーンです。
薄暗くなった森の中で泣いている子供のところに、顔が半分にかじられたアンパンマンが助けに来る。
いや、ちょっと待ってください!!!
そんな薄暗い森の中に、顔が半分の生物が現れたらそっちの方が怖くて迷子どころじゃないですよね。
さらに助けた子供に残りの顔もあげてしまい、最終的には顔が無くなってしまったのです。
下の子に初期アンパンマンの絵本を読んだ。
かなりエグかった、アンパンマン顔全部食べさせてしまってる。 pic.twitter.com/ERltHgmUQ1— ohkuma🦀🦞 (@oh_guma) October 8, 2018
顔なしのアンパンマンが飛んでるって怖すぎですよね。
現代のアニメでは、アンパンマンの顔が汚れたり濡れたりすると、途端に力が弱まって飛べなくなってしまいますが、初期設定では、なんと顔が完全になくても飛行も会話も可能だったのです。
首から上が真っ白な状態で、ふわりと空を舞うその姿は、率直に言ってかなり不気味でした。

口が無いのに話せるという設定も、なんだか昔ながらの設定とも感じます。
特に、パン工場で新しい顔を待つシーンは強烈です。
台の上に正座して、焼き上がりを待つ顔のないアンパンマン。
子ども向け絵本としては異質な光景に、当時の編集者も「これ以上は描かないで」と懇願したそうです。
ですが、不思議なことに、この設定を怖がる子どもはほとんどいなかったといいます。
むしろ、大人が想像する以上に、子どもたちはこの描写に引き込まれていったのです。
私は最近になって、その理由が少し分かるような気がします。
子どもたちは、アンパンマンの行動の純粋さに共感していたのではないでしょうか。
見返りを求めず、困っている人のために自分の全てを差し出す。
その無償の愛の形に、子どもたちの心は素直に反応したのかもしれません。
顔のないアンパンマンは、確かに見た目は怖いかもしれません。
でも、その姿には「他者のために自分を投げ出す」という深いメッセージが込められていたのです。
時代と共に表現方法は変化しましたが、この精神は今も脈々と受け継がれているのだと思います。
初代のアンパンマンが死ぬのは撃たれたから?

アンパンマンの初期作品『十二の真珠』(1970年)には、読者の心を深く揺さぶる衝撃的な結末が描かれていました。
空からパンを投下していたアンパンマンが攻撃を受けて姿を消すという、現代のアニメからは想像もつかない展開です。
この最初期のアンパンマンは、見た目からして現在とは全く異なります。
茶色の服とマントを着た、どこにでもいそうな中年男性。
頭巾をかぶったその姿は、正直なところ、ヒーローというよりも少し哀愁漂う存在でした。
顔もパンではなく、ただのおじさん。
パンを持ち歩いて困っている人に配るだけの、どこか切ない雰囲気の人物として描かれていたのです。
メタボなおじさんがアンパンを配ってた初期のアンパンマン。 pic.twitter.com/pvE1Aa34rG
— 考える猫 (@kbk55) January 19, 2024
また、現代版と大きく異なるのは、周囲からの扱われ方です。
他のヒーローたちからは「ニセモノ」と指さされ、「ニセモノおっこちろ!」と罵声を浴びせられる場面まであります。
パンを差し出しても「いらない」と断られ、「ソフトクリームの方がいい」と子どもに言われるシーンは、読んでいて胸が締め付けられる思いがしました。
これは、善意の行動が必ずしも周囲から理解されるとは限らないという、現実社会の厳しさを象徴しているように感じました。
そんなアンパンマンは、最期まで自分の信念を貫きます。
空腹に苦しむ子どもたちのために、上空からパンを投下し続けたのです。
しかし、その行為が誤って攻撃を受ける原因となってしまいます。
ただし、物語はここで完全に終わりではありません。
最後に「アンパンマンは決して死にはしない」という希望的なメッセージが添えられています。
「世界中のおなかのすいた子どもたちのために、アンパンマンは今もとびつづけている」という言葉には、深い愛情が込められているように感じます。
実は、この初期設定には重要な意味がありました。
やなせたかし氏は「人間は食べなくては生きられない」という現実と向き合い、そこから「逆転しない正義」という理念を追求するようになったのです。
つまり、初期アンパンマンの「死」は、実は永遠に生き続ける愛の象徴だったのかもしれません。
私たちが知っているアンパンマンは、この切ない初期設定から、長い時間をかけて進化してきました。
でも、その根底にある「困っている人を助けたい」という純粋な思いは、50年以上の時を超えて、今も変わることなく受け継がれているのです。
アンパンマン都市伝説まとめ

長年愛され続けているアンパンマンには、実に興味深い都市伝説が数多く存在します。
ジャムおじさん黒幕説
最も有名なのが「ジャムおじさん黒幕説」です。
これは、ばいきんまんの正体は実はジャムおじさんが作ったジャムパンマンが腐敗して生まれたという説です。
確かに、ジャムおじさんとばいきんまんの関係性には謎が多く、この説を裏付けるような描写もちらほら見られます。
ですが、これは良い人そうに見えるジャムおじさんが、実は悪事を働いていたという信じがたい設定を期待したファンの創作の可能性が高いです。
公式設定でも「ばいきんまんは赤ちゃんの頃にバイキン星からやってきた」とされているため、この説は真実ではなさそうですね。
アンパンマン食事拒否説
また、個人的に興味深いと感じるのは「アンパンマン食事拒否説」です。
アニメの食事シーンでアンパンマンが一緒に食べる描写がほとんどないことから生まれた噂です。
実は、これには明確な理由があります。
アンパンマンは顔のアンコをエネルギー源として活動しているため、普通の食事を必要としないのです。
子どもたちの中には「アンパンマンはみんなに顔をあげちゃうから、お腹すいてないのかな」と心配する声もあるそうですが、そこは安心してよさそうですね。
バタコさん結婚説
「バタコさん結婚説」も根強い都市伝説の一つです。
アニメ初期には、バタコさんとおむすびまんの間に微妙な雰囲気が漂う描写があったことから、「最終的に二人は結ばれるのでは?」という期待が高まりました。
しかし、現在ではそうした設定は完全に消えています。
バタコさんもそうですが、ジャムおじさんが結婚しているのかも分かっていませんね。
恋愛要素を抑えることで、より幅広い年齢層が楽しめる作品になったのかもしれません。
アンパンマン死亡説
最も衝撃的なのが「アンパンマン死亡説」でしょう。
これは、最終回でアンパンマンが命を落とすという噂です。
実は、この都市伝説には初期作品が関係していると考えられます。
1970年の『十二の真珠』では、アンパンマンが姿を消すという展開があり、それが誤って伝わった可能性が高いのです。
チーズがばいきんまんの手下説
また、チーズに関する意外な設定も話題になりました。
現在は愛らしいキャラクターとして親しまれているチーズですが、実は初登場時はばいきんまんの手下だったという事実。
アンパンマンは犬が苦手という情報を聞いたばいきんまんが、アンパンマンの元に送り込んだとされるのがチーズ。
ですが、チーズがアンパンマンに懐いてしまったため、パン工場に住み着いているようです。
そうなると、チーズは裏切り者ということになりますが、ばいきんまんの口からそのような発言は聞いたことがないので、事実かどうかはわかりません。
もし事実だとすると、そのことをバラさないばいきんまんは、実は仲間思いの優しいキャラということになります。
このように、アンパンマンには数々の都市伝説が存在します。
これらは単なる噂に過ぎないものもありますが、中には初期設定が基になっているものも。
こうした都市伝説の存在自体が、アンパンマンという作品の奥深さと、世代を超えた人気を物語っているのではないでしょうか。
初期のアンパンマンと現代版を比較
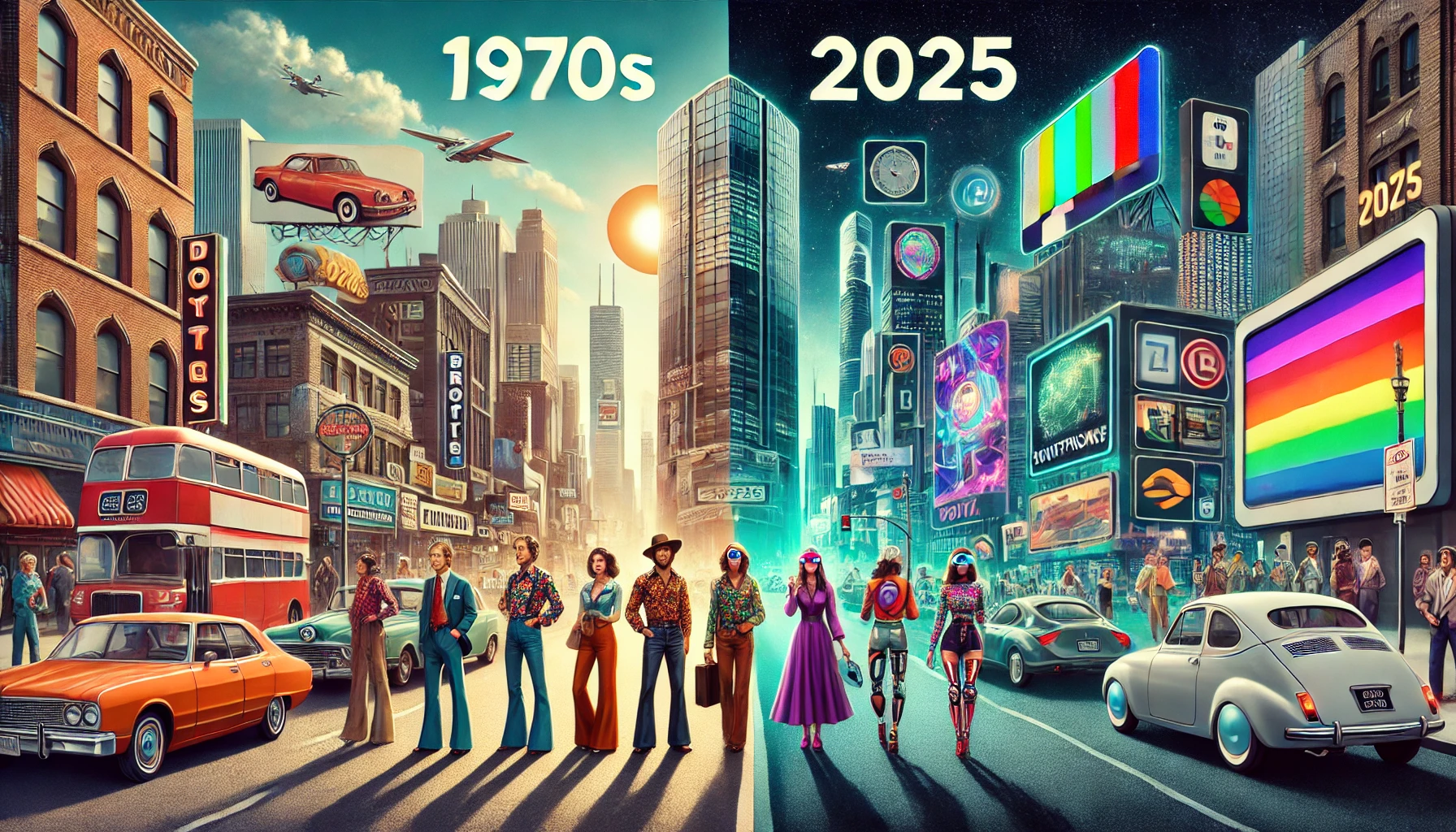
アンパンマンは50年以上の歴史の中で、大きく進化を遂げてきました。
その変遷には、日本の文化や社会の変化も映し出されているように感じます。
最も目を引くのは、外見の劇的な変化です。
デビュー当時のアンパンマンは、なんと茶色い服を着た普通の中年男性。
その後、顔がアンパンに変わっても、8頭身で手足には人間そっくりの5本指がありました。
それが現在では、親しみやすい3頭身のデザインに。
手はミッキーマウスのようなグローブ型になり、より可愛らしい印象に生まれ変わっています。
行動様式の違いも興味深いポイントです。
初期のアンパンマンは、困っている人に顔を直接かじらせていました。
顔が完全になくなっても平気で、首から上が真っ白な状態で飛び回るという、今では考えられない描写も。
対して現代版では、顔の一部をそっとちぎって手渡し、顔が汚れただけでも弱ってしまいます。
この変化には、子どもたちへの配慮が感じられますね。
物語のテーマも大きく異なります。
初期作品では、人間の苦しみや社会問題が色濃く描かれ、時にはアンパンマン自身が命を落とすような展開も。
しかし現代版では、愛と勇気、友情がメインテーマとなり、明るく希望に満ちた物語へと変化しました。
初期のばいきんまんは純粋な悪役でしたが、今では憎めないキャラクターに。
ただし、重要な点が一つあります。
それは「困っている人を助けたい」という根本精神が、50年以上経った今も変わっていないということ。
やなせたかし氏が追求した「逆転しない正義」は、形を変えながらも確実に受け継がれているのです。
個人的に感じるのは、この変化は決して「子ども向けに薄められた」わけではないということ。
むしろ、時代とともに進化しながら、本質的なメッセージをより多くの人に届けやすい形に昇華させていったのではないでしょうか。
アンパンマンは、これからも時代に合わせて少しずつ変化していくかもしれません。
でも、その核心にある「愛と勇気」のメッセージは、きっとこれからも変わることなく、子どもたちの心に届け続けることでしょう。
個人的に最も感動的なのは、50年以上もの間、「困っている人を助けたい」という核心的なメッセージが守り続けられていることです。
これは、時代を超えた普遍的な価値観の重要性を示していると考えられます。
まとめ

アンパンマンは50年以上の歴史の中で、大きな進化を遂げてきました。
特に初期と現代版では、キャラクター設定や表現方法に劇的な違いが見られます。
初期のアンパンマンは、8頭身の細長い体型に人間そっくりの5本指を持ち、時には顔のない状態でも飛行や会話が可能という、現代からすると不気味とも取れる設定でした。
困っている人に顔を直接かじらせる描写は、当時の関係者から「残酷すぎる」という批判を受けることもありました。
さらに、1970年の『十二の真珠』では、アンパンマンが姿を消すという衝撃的な展開も。
茶色い服とマントを着た中年男性として描かれ、他のヒーローたちから「ニセモノ」と罵られるなど、現代とは全く異なる切ない雰囲気が漂っていました。
一方、現代版では3頭身の愛らしいデザインに変更され、顔の一部をそっとちぎって困っている人に手渡すという優しい表現に。物語も明るく希望に満ちたトーンへと進化しています。
しかし、「困っている人を助けたい」という根本精神は50年以上変わることなく受け継がれています。
これはやなせたかし氏が追求した「自己犠牲の精神」と「逆転しない正義」という理念の表れであり、時代に合わせて表現方法を変えながらも、その本質は揺るぎなく守られ続けているのです。

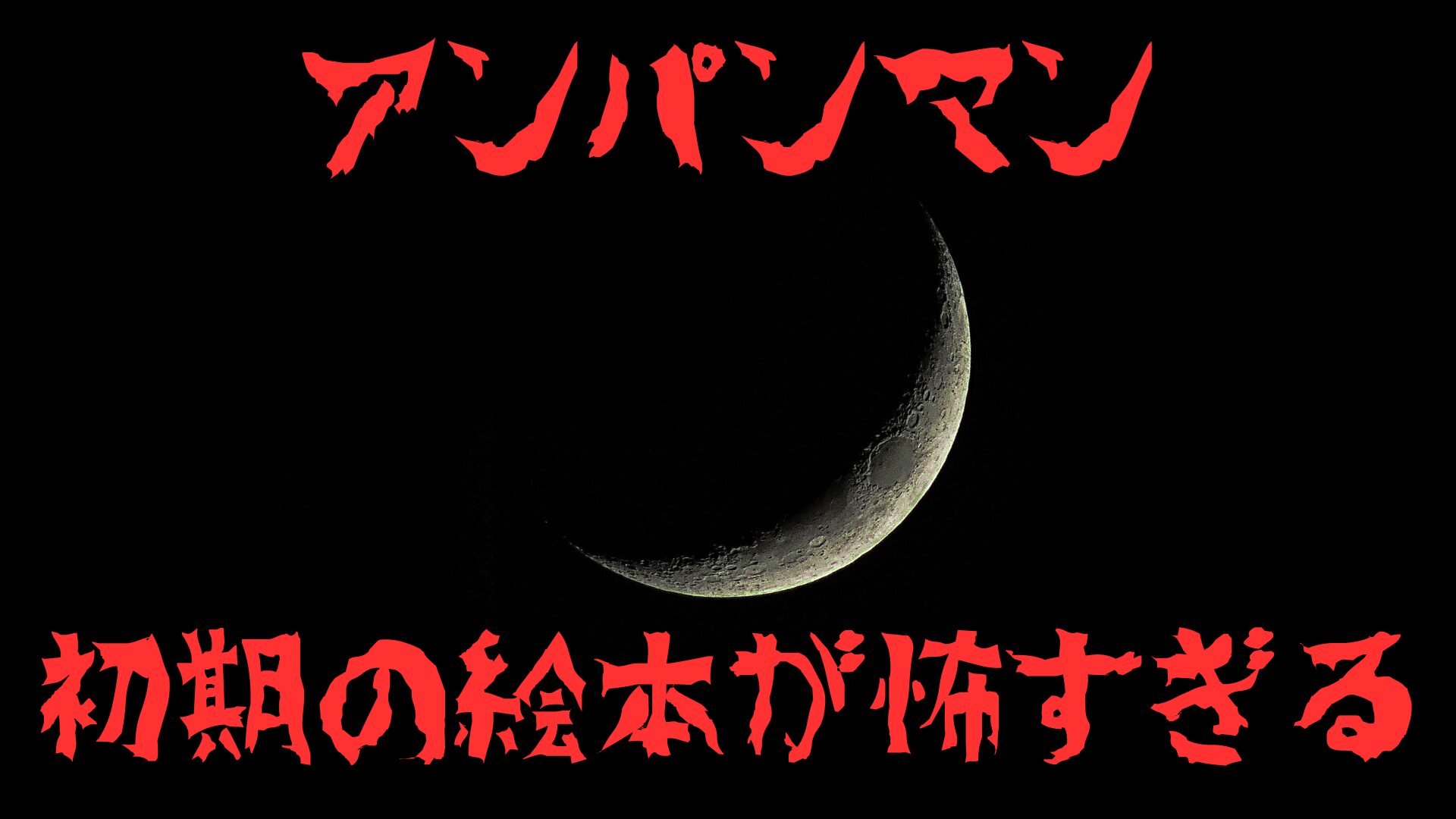



コメント